��b�T���Ƃ́A������2,500���~�ȉ��̐l�����鏊���T���ŁA���ׂĂ̔[�Ŏ҂��������ɍ���������l�I�T���̂ЂƂł��B��b�T���z�́A��{�I��48���~�ŁA���v�������z��2400���~�ȉ��Ȃ疞�z�̍T�������܂�
�i���R�j�ɂ���
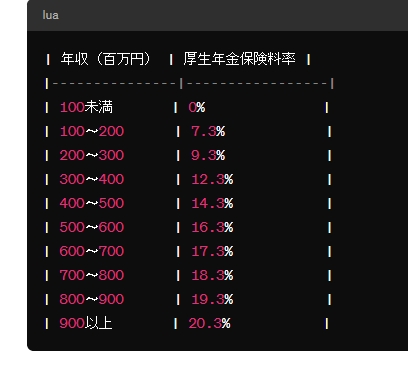
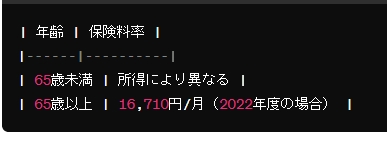
���E��킩��₷���ŋ��u��
���܂�����
���̏������u���E��킩��₷���v�V���[�Y���D�]�ɂ��A�ŋ��ɂ��Ă��L�������Ă݂����Ǝv���܂��B
�}�[�W�����ɂ��ẮA1998�N�Ɍ��J���܂������A�l�X�ȂƂ���Ő^������A�T�C�g�⏑�Љ��œ��e��_���W�J�̏��������̂܂܃p�N����Ƃ������Ƃ��N���Ă��܂��B
�ł́A�n�߂܂��B
���{�́A��{�I�ɂ��ݐi�ې��ł��B
�ݐi�ېŕ����Ƃ́A�������ς��҂��ł���z����͐ŋ����������낤���B���҂��ł��Ȃ��n�R�l����͐ŋ����܂���̎~�߂Ƃ������A���ĕ����ł��B
�Ȃ�ł����Ȃ��Ă�̂��͒m��܂���B�ł��A���{�͊�{�I�ɂ��̗ݐi�ېłł���Ă��ł��B
�܂����{�ɋ������H���C���^�[�l�b�g���������d�C���Ȃ�̃C���t�����Ȃ����������z�����Ă݂ĉ������B
�����������Ƃ��Ȃ����n����B����Ȏ���ɁA��������l�̐l�Ԃ����̐l�Ԃ̉��\�{�����S�{������{���x�邱�Ƃ��\�������ł��傤���H
�������A���E���������͂��ł��B�����ɂ͂��܂�n�x�̍�������܂���ł����B
�������A��l�B���z���Ă��ꂽ�V�X�e����C���t������肭���p���邱�ƂŁA���҂̉��\�{�����S�{���̕x�������I�ɓ��邱�Ƃ��ł���킯�ł��B
�ł�����A�u�������O�B����Ȃɋ������Ă邪�A�������̐�l�B���z���Ă��ꂽ�V�X�e�����Ŏg���Ă邶��˂�����I�I�s���̂����b���I����Ȃ炻�̕��ŋ�������I
���Ƃ����A�݂�Ȃŗ��p������č���������A���O��l�ʼn��\�{����ЂƂ��ė��p���Ă����ȁB��Ђ̎Ԃ����̋��Ɉ�����������H�������ď��ނ��C�U���K�v���B�������p�������Ƃ��Ȃ��l������Ȃ��ŁA���O�����������x�����x�����p���Ă��ĉ�Ђ̎����Ă���̂ɁA�ŗ��������Ȃ�ĕs��������B�����炨�O�͂����Ɛŋ�������I�v
���ĂȂ�̂��S��Ȃ킯�ł��B���ꂪ�ݐi�ېł̍l�����ł��ˁB
�܂��t�ɁA���̗ݐi�ېłƂ����̂́A�l�����ɂ����܂����A
�u�v���C�x�[�g���]���ɂ��ĂƂɂ��������҂��A�Ƌ����҂��܂����Ă��ŋ��Ŏ���銄���������Ȃ邵�A�t�ɁA
�v���C�x�[�g�D��I�������������Ă��A�z�炵�����炳�����ƒ莞�ŋA���ĉƂŃQ�[�������菗�V�т����肵����`�`���ƁB�Ȃ�čl���ăe�L�g�[�ɓ����Ď����̒Ⴂ�l����́A���܂�ŋ����̂�߂Ƃ����ˁv
���ĕ��j�ł���Ƃ�������킯�ł��B
�܂��A�Ƃɂ����A�Ȃ��ݐi�ېłł���Ă���̂��͂킩��܂��A���{�͊�{�I�ɂ͂���ł���Ă��ł��B
������A���{�ɐ��܂ꂽ����ɂ́A�������قǂقǂɁB
�v���C�x�[�g���]���ɂ��Ă��������������Ƃ���ŁA�ŋ��������Ȃ�킯�ł�����A
�u����ȏ�҂��ł��ŋ��Ŏ����čs����邾��������A�����͂�������ȏ㓭���̂�߂Ƃ����Ɓv
�ƍl����l�����ɂ͂���킯�ł��B���ۂɎ���҂���ł����������l�����Ȃ��Ȃ��ƕ����܂����B
�t�ɁA�����V�тق����Ă��Ă������������ł��ˁB�ǂ����Ă��_���_���Ƃ��Ă��܂��܂�����A�����ɂ������n�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�����A���������Ɖ߂������߂ɂ́A�K���������������炢�͂��������̂ł��B�����炱���A����
���N���Čy���d���ɍs�����炢�̂��Ƃ́A�Œ���A�l�͂����ق����悢�̂�������܂���B
�Ƃɂ����A���{�͗ݐi�ېłȂI���̂��Ƃ͍ŏ��ɒm���Ă����Ă��������B
���p��Ƃ܂Ƃ�
�u����N���v�Ƃ́E�E�E�u����v�Ƃ������A���^�Ȃǂ���ŋ����̑����������������z�̂��ƁB
�u�N���v�Ƃ́E�E�E�P�N�Ԃ̑��x���z�̂��ƁB�ŋ��Ȃǂ��������O�̋��z���w���Ă���B
1��1���`12��31����1�N�Ԃʼn�Ђ���x����ꂽ���^��e��蓖�A���ԊO�蓖�Ȃǂ̐ŋ����������O�̋��z�̂��ƂŁA���x���z�ƌĂ�܂��B
��Ђ���x�����邷�ׂĂ̎����̂��ƂŁA�u�z�ʁv�Ƃ��Ă�܂��B
1�N�Ԃ�ʂ��Ď�������^�����̍��v���u�N���v�ƂȂ�܂��B
�u�����v�Ƃ́E�E�E��������K�v�o������������z�̂��ƁB
�u�ېŏ����v�Ƃ́E�E�E�ŋ����������鏊���̂��ƁB
�u�Љ�ی��v�Ƃ́E�E�E�u��Õی��i���N�ی��j�v�u�N���ی��i�����N���ی��Ȃǁj�v�u���ی��v�u�ٗp�ی��v�u�J�Еی��v�̂T���w���B�����́A���̂����A�J���ی��ȊO�́A���^����A�ی������T������܂��B
���Ȃ݂ɁA �J���ی��ɂ�����J�Еی��̕ی����́A���Ǝ�݂̂����S���A1�N�����܂Ƃ߂Ďx�������߁A�]�ƈ��ɕ��S�̋`���͂���܂���B
���̂����A��Õی��ƔN���ی��A���ی��́A�����N��ɒB�����Ƃ��ɁA�K����������`��������܂��B
���ɂ��A��Ј�����������u���N�ی��v�u�����N���v�u�ٗp�ی��v�u�J�Еی��v���܂Ƃ߂āu��p�ҕی��v�A
���c�Ǝ҂Ȃǂ���������u�������N�ی��v�u�����N���v���܂Ƃ߂āu��ʍ����ی��v�ƌĂԂ��Ƃ�����܂��B
https://hoken-all.co.jp/hoken/social/
�i����j���i�i�N���j�|[�ېŏ����i�i�N���j�|�i�Љ�ی����i�N���A���N�ی��j�j�p]�~�ŗ��j�|�s����
�����ŁE�E�E�����ɂ������Ă���ŋ�
| �����ł̎�� | �����ې� | �����ې� | ||
| �ŗ� | �ݐi�ې� | ���v�̂Q�O���i�����Łi���Łj�P�T���A�Z���Łi�n���Łj�T���i���������ސE�����͒��ߗݐi�ېŁj | ||
| ���� | �e��̏������z���ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��� �ŋ����v�Z����B |
�������ĐŊz���v�Z����B | ||
| �m��\�� �N������ |
�\�������ې� | �����ې��i�m��\���s�v�j | ||
| ���c�ƂȂǁA�m��\���Ŗ{�l���\������B | �T�����[�}���͉�Ђ��\�����Ă���Ă���B�����Ƃ����A�N�������ő����Ԃ��Ă���B | �m��\���Ŗ{�l���\������B | �����ɂ�莩���I�ɔ[�t�����B�i�m��\���s�v�j | |
| �����̎�� | ����8��ނƂȂ�܂��B �����q�����i�����ېłɊY�����Ȃ����́j ���z�������i�����ېłɊY�����Ȃ����́j ���s���Y���� �����Ə��� �����^���� �����n�����i�����E�����E�y�n���������́j ���ꎞ���� ���G���� |
�E���������i���n�����j �E�敨��� �E�I�v�V������� �E�b�c�e��� �E�e�w��� ���Z���i�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���́i���⍑���e�w�j �E�ސE���� �E�R�я��� |
�a�����̗��q | |
| �E�C�O�e�w �E�C�O�o�C�i���[�I�v�V���� |
�E�����e�w �E�����o�C�i���[�I�v�V���� |
|||
| �\�� | ���^�����ȊO�Ɋm��\�����K�v�Ȃ̂͂Q�O���~�ȏ� | |||
| ���� | ���̔N�� �P���P���`�P�Q���R�P���܂ł̂��̂� ���N�̂Q���P�U������R���P�U���܂ł̊ԂɁA����m��\��������B |
�s�v | ||
| ���� | �������� | �������� | �m��\���s�v�i���Ă͂����Ȃ��j�A�����ł͂Ȃ����� | |
�������ł̐ŗ��Ƒ����\�i�����Q�V�N�ȍ~�j
| �ېł���鏊�����z | �ŗ� | �T���z |
|---|---|---|
| 195���~�ȉ� | 5% | 0�~ |
| 195���~���`330���~�ȉ� | 10% | 97,500�~ |
| 330���~���`695���~�ȉ� | 20% | 427,500�~ |
| 695���~���`900���~�ȉ� | 23% | 636,000�~ |
| 900���~���`1,800���~�ȉ� | 33% | 1,536,000�~ |
| 1,800���~���`4,000���~�ȉ� | 40% | 2,796,000�~ |
| 4,000���~���` | 45% | 4,796,000�~ |
���Ƃ��A�ېŏ������Q�O�O���~�̏ꍇ�A�Q�O�O���~�̂����A�P�X�T���~�܂ł͂X�V�T�O�O�~�i�T���j�A�c��̂T���~�ɂ��āA�ŗ��P�O���Ƃ���Ƃ������Ƃł��B
������ȒP�ɂ����̂��A�Q�O�O���~�ɂP�O�������������z���o���āA�T���z�ł���X�V�T�O�O�~�������Έꏏ����ˁA���ĈӖ��ł��B
�ېł���鏊�����z�F500���~�̏ꍇ
������25�N�i2013�N�j����ߘa19�N�i2037�N�j�܂ł́A��L�̏����łɉ����āA�������ʏ����Łi�����Ŋz��2.1%�j���������܂��B
���p������A��b�m����
������E�E�E�i�x�����O�̒i�K�Łj�x���������������Ĕ[�t����Ƃ����Ӗ�
���،���Ђł́A���N�̔��p�����N�ȍ~�̔��p�v�v�ʎZ���Ă���܂���B�i1�N�Ԃ̎���ɑ��ẮA���v�ʎZ���Ă���܂����B�j
���ɍ��N100���~�̔��p��������A���N120���~�̔��p�v���������ꍇ�A���N�̔��p���𗈔N�m��\�����A���N�̔��p�v���ė��N���邱�Ƃɂ��A���N�̔��p�����v�ʎZ���邱�Ƃ��o���܂��B
�m��\���ŌJ��z���ꍇ�� ���̊� �m��\�����p�����Ȃ��Ƃ����܂���
���N�}�C�i�X�� ���N����Ȃ��ł� �m��\�����}�C�i�X���������p���K�v������܂��B�i�ŋ��̉ߕs���ɊW�Ȃ��Ă��\�����܂��B�j
���}�C�i���o�[���x
�}�C�i���o�[���x�ɂ��A�����̓K���X����ł��B�V�N�Ԃ����̂ڂ��Ēǒ��ېł�����܂��B�ŋ��͔j�Y�̑ΏۊO�ł��B
���N�ԂQ�O���~�̕��Ǝ������Ȃ���ΐ\�����Ȃ��Ă��ǂ��B�������Z���łɊւ��Ă͕ʁB
�Z���ł͖����̊NJ��B�����ł͐Ŗ����̊NJ��B������A�Z���ł͂������Ă���B
�܂�A�Ŗ����ɑ��Ċm��\���͂��Ȃ��Ă��悢�̂�����ǂ��A
�������x���ɂ͐\�����K�v�B�Q�O���~�ȉ��ł��K�v�B
�����{��������������������ł���Ă� �N�ԗ��v���}�C�i�X�̎� �ǂ��Ȃ邩
�P�ЂŎ���̏ꍇ�A
�،���Г��ő��v�ʎZ�����̌��ʃ}�C�i�X�̏ꍇ ���̂܂܂ɂ��Ă����Ă��n�j�ł��B
�܂��z���������������z�������ɂ��Ă����� �،������Ŏ��悤�ɂ��Ă�����
��������v�ʎZ���Ă���܂����� �z�����Ō�������Ă��Ă� ���̏،���ЂŃ}�C�i�X�ɂȂ��Ă����
�،���Ђő��v�ʎZ���Ă���܂����� �z�����̌��������߂�܂��B
��������̓����Ƃ��Ă����ЂƂ� �����̌J��z�����ł���Ƃ���ł��B
�R�N�ԌJ��z���܂��̂� ���N�}�C�i�X�ł����N�ׂ����o���ꍇ
�����N�ő��v�ʎZ�ł��܂��B
���������N�ی��͑O�N�x�̏����ɂ���ċ��z�����܂�B
�����z�ʉ݂̐ŋ��ɂ��č��ł�萳���ɃA�i�E���X���ꂽ�̂́A�Q�O�P�V�N�X���P�O��
���~��jpy�ǂ�����t�B�A�b�g�ł����H
Fiat Money��Fiat Currency�̗���ŁA�@��ݕ�(�@�莆��)�̂��Ƃ��w���܂��B
�@��ݕ��Ƃ͓��{�~�iJPY�j��č��h���iUSD�j�ȂǍ������s���Ă��邨���̂���
����Ô�T����N���ɂ���ꍇ�A
�N�ԂɈ�Ô���ёS�̂łP�O���~������߂��Ă���B
�����Ɋւ��Ă͐\�����K�v�B�����ł��Ŗ����ɐ\�����K�v�B
������҂Ȃǂɂ����Ă����R�f�Âł͍T���̑ΏۂɂȂ�Ȃ��B
�ی��̐f�Â͂P�O���~����������S�Ė߂��Ă���B��ʔ���B
�܂��A���ׂ������ĕ��ז���Ă���Ô�Ɋ܂܂��B
�l�ԃh�b�N���ĕa�C�����������ꍇ�́A���N�f�f��p����Ô�Ɋ܂܂��B�R�����܂߂Đ\�����K�v�B
���m��\���ɂ���
��Ј��͊m��\���͂��Ȃ��B��Ђ��\�����Ă���Ă���B
��Ј��͖������^����V��������āA��������Ă���B
���ꂪ�N�������Ƃ����`�Ŗ߂��Ă���B���߂ɒ�������Ă��邩��B
�ی��̒ʒm�Ƃ��������čs���Ɗҕt�����B����͊ҕt�ƌ������a���Ă�������Ԃ��Ă��Ă��邾���B
�ʏ�Ȃ��Ђ��Ŗ����ɋ��^������\������B
����Őŋ������܂�̂ŏ����ł͂����ŕ����B�Ŗ������������ɒʒm���s���B
�l�͎����ŐŖ����ɐ\���ɍs���B������R���P�T���܂łɔ[�ł���B
�̂��̂����������Z���ł̒ʒm�����邩��R���r�j�Ȃǂŕ����B
����������Ƃ��u���^�����v���炵���ŋ���������Ȃ��悤�ɂȂ�B
��Ј��̏ꍇ�͗��N�̋��^���略���B
�Z���ł͑O�N�̏����ɑ��Đŗ������܂邩�痂�N�Ɏx�����B
���N���O�͎���ɒʒm�����Ă����B
���ʒ����ɂ���Ή�Ђɂ�Ȃ��B��������Ȃ��悤�ɁA�m��\���p���Ɂ�������B
�����Ŏx�����Ƃ������ƁB
�������A�����͖ʓ|�����疳�����ĉ�Ђɒʒm���o�����肷��B
�����̏Z��ł�������̐Ŗ��ۂɓd�b��������B
��Q��A
| Question | Answer | |
| �P | ���g���[�h���ē�������i��������j�ɂ��Ă����A�N�ԂP�O�O����P�O�O�O����P�O�O�O�O����g���[�h���Ă��A��A�ŋ��W�̎葱���̂��Ƃ͐S�z�����ɂ悢�̂ł��傤���H�،���Ђ�����ɂ���Ă�����ł���ˁH |
�͂������ł��B �������A�������o���ꍇ�́A �@���̂܂܉��ɂ����Ȃ��B �A�������m��\�����đ������J�z���B �̂ǂ��炩��I�����܂��B |
| �Q | H30�N �{�P�O�O���~ H�R�P�N �|�P�O�O�O���~ H�R�Q�N �{�T�O�O���~ H33�N �{�V�O�O���~ H�R�S�N �|�Q�O�O���~ |
H30�N��+�ł����牽�ɂ����܂���B H31�N�́[�Ȃ̂Ń}�C�i�X�����m��\�����܂��B 1,000���~�̑����J�z�B H32�N+500�����m��\�����܂��B�����z100�����\���B �O�N�iH31�N�j��?1,000����+500���v�ʎZ���ā[500���B ���̉ېŏ�����0�~�ɂȂ�A�J�z�����́[500���Ɍ���B ���̉ېŏ�����0�~�Ȃ̂Őł�0�~�B ������100���~�A��������Ă���̂Ŋҕt�����B �i���m�ɂ͐Ŗ�������75���A�s�����������25���j �܂�A���N�x�ȍ~�̊m��\���Ɂ|�T�O�O���~�Ƃ��Ďc��B H33�N��+700�����m��\�����܂��B�����Ŋz140�����\���B �O�N�iH32�N�j�̌J�z�����[500����+700���v�ʎZ���� +200���̉ېŏ����Ɍ���܂��B 200���̐ł�40���B +700���Ō������ꂽ�z140������{�N�ېŕ���40�������� ������100�����ҕt�����B �J�z�����͑S���g�������̂ŁA�J�z�����͂O�ƂȂ�B H34�N�́[200�����m��\�����đ������J�z���B ���̌J�z������3�N�ԗL���Ȃ̂ŁA�J�z�z���O�ɂȂ�܂�3�N�Ԃ� �m��\�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�`���ł͂Ȃ��C�Ӂj ���\���̔N������Ǝ�������B |
| �R | �m��\���ɂ��Ď���ł��B������ɂ��Ăł��B �Q�O�P�X�N ���v�|�X�O���~ �Q�O�Q�O�N ���v�{�P�O�O���~ ����ƁA�{�P�O���~���ɂ��Đŋ����������Ă���킯�ł���ˁH ���ۂ̏،������ł́A��������A��������Ƃ��Ă��邽�߁A �Q�O�Q�O�N�́{�P�O�O���~������Ɉ�����Ă���킯�ł���ˁH ������{�P�O�O���~����ł͂Ȃ��{�P�O���~��������Ă��炤���Ƃɂ���ɂ́A �ǂ������葱�����Ƃ�Ηǂ��̂ł����H |
��(��������̑��v�ʎZ) ���v�ʎZ�͂��̔N�x�̂P���`�P�Q���̎���ɂ����̓s�x �������ōs���܂��B���N�P�� (�����̌J�z�\��) 2019�N�x����90���~���̐\�������� (2020�N�x) �������ɂ����Ắ{100���̑��E���肪���Ȃ��B����č��z10���~�̐\��������B |
|
��������č��z10���~�̐\��������B �ł��u��������̌�������v�ɂ��Ă���̂ŁA�،���Ђ���͏���ɂP�O�O���~���ɑ��Ă̐ŋ������łɎx�����Ă���킯�ł���ˁH ����͂ǂ�����Ď��߂��̂ł����H |
���m��\���͑��X�̏��𐴎Z����ƌ����@�\������܂��B ��̓I�Ɍ����Ǝ��̗l�ɂȂ�܂��B �@2020�N���̏����z���v�Z����(100���ׂ����B�ł��J�z������90�����������B�����10���̏�����) �A�@(10��)�Ɍ������Ŋz���Z�o����B �B�����Ŋz�Ɣ�r����B(�Ƃ���Ŋ��ɔ[�ł��Ă���ŋ��͂Ȃ��������ȁB�������A100���̏��n�v�ɌW��ŋ���������) �C�A-�B=�}�C�i�X�ɂȂ������B(���ꂪ�ҕt��) |
|
|
���Ȃ�قǁB�Ƃ������Ƃ́A�m��\�����ɂ��ׂď������Ƃ͊ҕt��������킯�ł��ˁH�H�H ���ƌJ�z�����X�O���~�Ƃ����̂͂Q�O�Q�P�N�ɂ���Q�O�Q�O�N���̊m��\�����ɂǂ�����Ēm�点���ł����H�Ŗ����ɁB�Ŗ����ɍT���������ł��傤���H�����炻���M���ď������߂�����ł����H����Ƃ��Q�O�Q�O�ɑ����̊m��\�������R�s�[���o����̂ł����H |
���@2019�N�x���̐\���Ŋ��̏��n�����o���ƋL�ڂ���B(���N�ɌJ�z�T��������ׂł���A���̐\�������Ȃ��Ƃ��̌J�z�T���̌�����r���B����ĐԎ��ł����Ă����N�ȍ~�ׂ̈ɐ\��������) �A2020�N�x�̐\���ł́A�O�N�̐\����(�@)�̂��̑����z��]�L����B(�Ŗ������@�̃f�[�^��L���Ă���) �]�L�͂����p�̏��ނ����邩��A������g�p����B |
|
| �S | �Q�O�P�X�N�A���̓}�C�i�X�ł��B ����ŁA�u��������A��������v�Ŏ�������Ă��܂��B �ŁA�Q�O�P�X�N�Ɍ����͂���Ă���̂ł��傤���H����Ƃ��}�C�i�X�����炳��Ă��Ȃ��̂ł��傤���H �Ƃ����̂́A�Q�O�P�X�N�̑O���̓v���X�A�㔼�͂������}�C�i�X�ł����̂ŁA�g�[�^���Ń}�C�i�X�Ȃ̂ł��B �v���X�̕����ł��łɐŋ����Ƃ�ꂿ������肵�Ă��܂����H |
��������������̓����ł́A����̓s�x�A���v�E���A����ɘA�����Đŋ������Z����܂��B����āA���ǃ}�C�i�X�ł��̔N���I�������ꍇ���ׂĂ̌���ł͌����ɖ߂��Ă��܂��B 暌���Ђ���̔N�Ԏ�����̌����Ŋz�i�����Łj�̗��y�� �������n���������z�i�Z���Łj�̗��͂��ꂼ�[���\���ƂȂ��Ă���͂��ł��B |
| ���E�v���`�i����̐ŋ��ɂ��ċ����Ă��������B | ���E�v���`�i�E��p�����ꍇ�A���n�����ƂȂ�A�����ېł̑ΏۂƂ��Ċm��\�����K�v�ƂȂ�܂��B �Ȃ��A�ۗL���Ԃɂ��ېŋ��z���قȂ�܂��B ���n�����̌v�Z���@�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B ���ۗL����5�N�ȓ� �Z�����n���������p���i�|�i�擾���i�{���n��p�j�|���ʍT��50���~ ���ۗL����5�N�� �������n�������o���p���i�|�i�擾���i�{���n��p�j�|���ʍT��50���~�p��2 �����A�v���`�i�ɂ��܂��Ă�1��̔��p�ɂ��200 ���~������n������������ꍇ�́A�x���������Ŗ����ɒ�o����܂��B�i�l�̂��q���܁j �Ŗ���̂����k�E�����〈�́A�ŗ��m���̐��Ƃ⏊���̐Ŗ����ɂ��m�F���������B�܂��A�ŏI�I�Ȕ��f����ь���́A���q���܂����g�̐ӔC�ł��肢�������܂��B |
���{�����̊�������ŗ��v���o���ꍇ�A**�����Ƃ��ē�������i��������j**�𗘗p���Ă���A�،���Ђ��ŋ��������I�ɒ������Ă���邽�߁A�m��\���͕s�v�ł��B
���m��\���ŏ����������
�k����������́l
�@�u�i��������j�N�Ԏ�����v�iSBI��HP�������ł���B�j�i�ꏊ�FSBI�،��ł́AHP��������Ǘ����d�q��t���ʁ��^�p�����{����1��16���O��Ɂu����N�Ԏ�����v�d�q��t�̂��m�点�ɒʒm�����Ă���B�˕ۑ��E������o����j
�A��Ӂi�ƌ����Ă��邪�A2021�N�̐\�����͎��Q�������Ǖs�v�������B�j
�B�����[
�C�}�C�i���o�[�ԍ��̂킩�鎆
�D�g���ؖ���
�E�U�荞�݁i�ҕt�j������s�̌����i�ʒ����J�[�h�s�����ԍ��̂킩����́t�j�i�ҕt�����ꍇ�j
�y�����z
�Q�O�P�X�N�@���łW�W���~�H�̑������m��\���ς�
�Q�O�Q�O�N�@���łP�O�O���~�̑������m��\���ς݁B
���N�x�ȍ~�����Ŋm��\������ꍇ�B
�Ȃ�ƂȂ��ł������������B
�܂��A�����[�ƔN�Ԏ�����A���̂Q��������A�����ɂ�����Ă��鐔������͂��Ă��������B
��J�������A�Ŗ����E���ł��ԈႦ���̂��A�Q�[�t�Ŋz�R�ҕt�Ŋz�@���̂�����B
���\���́u���ʒ����v�ŁB
�u��ʌ����v��u��������i�����Ȃ��j�v�𗘗p���Ă��āA�N��20���~�ȏ�̗��v���o���ꍇ�ɂ́A�����Ŋm��\�������Ĕ[�ł���K�v������܂��B�����łЂƂ|�C���g������܂��B�m��\��������Ƃ��́A�m��\�������\�u�Z���łɊւ��鎖���v�́u���^�����E���I�N�����ɌW�鏊���ȊO�̏Z���ł̒������@�v�Łu�����Ŕ[�t�i���ʒ����j�v��K���I�����܂��傤�B�������邱�ƂŁA���^�����ɂ�����Z���ł́u���^�V�����v�A���̗��v�ɂ�����ŋ��́u�����Ŕ[�t�v�ƕ����Ĕ[�߂邱�Ƃ��ł��܂��B����Ȃ犔������Ă��邱�Ƃ���Ђɒm���邱�Ƃ͂���܂���B
����Ђ̌o��������Ă�����e
�@��Ђ��������Ј��Ɏx�����i�����ŁA�Z���ŁA�i�L���Ӗ��ł́j�Љ�ی����������ċ������j
��
�A���̎x���������z����Ђ�
�E�u�n�������́i�Ј��̋��Z����s�����j�v�Ɂu���^�x�������������[�Ɠ������́v�Ő\������B�����ɁA�Z���ł��x�����B
�E�u���^�x�����������̏��ݒn���NJ�����Ŗ����v�ɂ́A��Ђ́A�����A�����ł��x�����B�i�����Ɍ��N�ی����A�����N���ی����͈������Ƃ���������B�ٗp�ی����͔N�ɂP��̔[�t�Ȃ̂ŁA����܂ŗa����B��������̌J��Ԃ��B�j
��
�B�e�����̂���́A�T�`�U�����A�e�l�́u�Z���Ō���ʒm���v������B�܂�A���^�x�����������s�撬���́A��R�`�S�J�������đS���̏Z���ł��v�Z���A���ʒ����̐l�͉�ЂցA���ʒ����̐l�͎���ցA����ʒm���Ɣ[�t���𑗂�܂��B
���̊ԂɊm��\���̊��������āA�m��\�������l�͐Ŗ�������s�����։�t����܂��̂ŁA���̐l�B�̌v�Z�̂����������܂��B
��
�C���̒ʒm�����ɁA
�E�u���ʒ����v�Ȃ�ΏZ���ł���Ђ��Ј��̑���Ɏx�����B6�����痂�N5���܂ł�12��ɕ����āA�Z���ł������̋��^����V��������Ă��܂��B
�E�����ɁA��Ј���3/16���܂łɊm��\�������Ă���A�s���ł��u���ʒ����v�ɂ��Ă���ꍇ�́A�Ј��̎���̏Z���Ɂy���z���t�����B���ʒ�����6���A8���A10���A1���̔N��4��ł��B
�i���@�m��\�������l�����ʒ�������]�����Ƃ��Ă��A�{�Ƃ̋��^����Ƃ��S�z�ʒ����ɂł���킯�ł͂���܂���B���Ƃ����^�ȊO�̏ꍇ�A���̕������ʒ����ɂł���Ƃ������Ƃł��B��Ђ����ʒ����ŋ��^�x�������o�����Ј��́A��{�S��(��ېł̐l��������)�A��Ђɑ����Ă��܂�����B����Ƃ͕ʂɁA����ɂ��͂��l������B�Ƃ������Ƃł��B�j�i�܂�A���^�͓��ʒ����̂݁B�I���ł��Ȃ��B�j
��
�D�N������
�e�l�����o���ꂽ��������ɁA��Ђ͔N������������B
�]�ƈ��ɂ́u�����[�v��n���B�]�ƈ������N�P���P���ɏZ�������鎩���̂Ɂu�����[�v�Ɠ��e�������u���^�x�����v���o����B�i���̎��A�u���ʒ����v�ɂ���l�́A�ǂ����āA���ʒ����ɂ���̂����R�����������B�j
��
�E�u�@�蒲���v�������̐Ŗ����ɒ�o�i�@�l������Ƃ���̐Ŗ����ɂ܂Ƃ߂āj
��
�F�Q�� �����ȊO�Ɏ���������l�́u�m��\���v������B
�u�m��\���v�́u�Z���Łv�̐\�������˂Ă���B
���Ƃ����^�����̏ꍇ�́A�u�N���������ρv�́u���^�x�����v�������̂ɍs���Ă���̂ŁA�����̂Ŏ��������Z���ďZ���ł��v�Z���A�{�Ƃ̕��ɒ�������悤�ʒm������B
���i��j�N���V�O�O���~�̐l���x�����ŋ��Ǝ���́H
| �P�D�����N���ی���700�~17.3�����P�Q�P���~ �Q�D���N�ی����F�V�O�O�~9.15�����U�S�D�O�T���~ �����̎Љ�ی��������v����ƁA��181.5���~�ɂȂ�܂��B�i�ٗp�ی����͖����j�E�E�E�i���P�j �R�D���^�����T��180���~ �S�D��b�T���S�W���~�E�E�E�i���Q�j �ېŏ�����700���[�i180���|48���|185.1��)��286.9�� �����Ł�286.9���~10%�|97,500��18��9,400�~�E�E�E�i���R�j �������ʏ����Ł�18��9,400�~2.1%��3,977�~ �Z���Ł�294,700�i�}1,500�����̂ňႢ����j�E�E�E�i���S�j ����=700���~-�i185.1���{18.94���{0.3977�~�{29��4700�j���S�U�U���~ |
�i���Q�j�ɂ���
��b�T���Ƃ́A������2,500���~�ȉ��̐l�����鏊���T���ŁA���ׂĂ̔[�Ŏ҂��������ɍ���������l�I�T���̂ЂƂł��B��b�T���z�́A��{�I��48���~�ŁA���v�������z��2400���~�ȉ��Ȃ疞�z�̍T�������܂�
�i���R�j�ɂ���
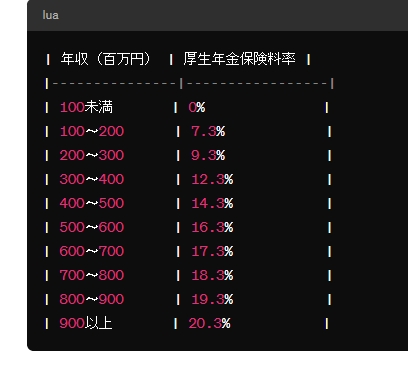
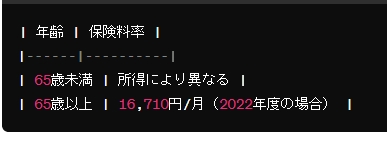
���Z���łɂ���
�Z���ł́A�s���{����s�撬������������ŋ��ŁA����������l�ɂ�����܂��B�ېŏ�����10%���ŗ��ł�
�Z���łɂ́A�������z�ɂ�����炸��z�ʼnېł�����ϓ����ƑO�N�̏������z�ɉ����ĉېł����������������܂�
�ϓ����́A�������z�ɂ�����炸��z�ʼnېł���܂��B���{�����ł�1500�~�i�W���ŗ��j�A�s��������3500�~�i�W���ŗ��j�ł��B����26�N�x����ߘa5�N�x�܂ł�10�N�Ԃ́A�W���ŗ��̓���ɂ�蓹�{�����ŁE�s�������ł̋ϓ����̐ŗ��i�W���ŗ��j�ɂ��ꂼ��500�~�����Z����Ă��܂��B
�������́A���̔N�̏�������Ɍv�Z���鏊���łƂ͈قȂ�A�O�N�̏�������Ɍv�Z�����Ƃ����_���|�C���g�ł��B�Z���ł̏������̐ŗ��́A�����Ƃ���10���ł��i���{������4���A�s��������6���j�B
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10221220225
| �Z�~�i�[��p�͉ߋ��̂��̂ł��悢�́H���̔N����H |
|
�Z�~�i�[��p��FX�̌o��Ƃ��Čv�シ��ہA��{�I�ɂ͂��̔N�ɔ����������������o��Ƃ��ĔF�߂��܂���B ���R
|